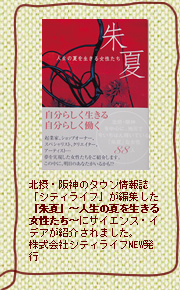今月のテーマ:砂糖の科学
晴れた日は日差しがまぶしく感じられるようになってきました。春ですね。桜の開花が待ち遠しい季節になりました。そして、学年末、新学年へと何かと気忙しい季節でもあります。あまりありがたくない花粉も今年は例年より多く飛散しているとか、三月は心躍ると共に悩ましい季節でもあるのですね。
今月のテーマは砂糖です。砂糖はどのように作られ、どのような特長があるのか、調べてみました。皆さんに持ち帰っていただいた「さとうきび」「べっこうあめ」のお味はいかがでしたか。甘さを味わって、少しほっとして、新しい学年へ備えていきましょう。
|
6年目に思うこと 3月11日、東日本大震災から6年をむかえました。残念ながら、被災地の復興はまだまだ不十分で、あの災害が如何に大きいものであったのかということを改めて感じずにはおれません。あの震災の翌月、小学校に入学した子供たちも今月、小学校卒業です。子供たちの成長を見ると、年月が経ったのだと実感しますが、被災地の状況を見聞きすると、まだそこまでしかできないのだなという感もあります。 そんな中、報じられたニュースの中に、福島より避難している方たちへのいじめ問題がありました。大地震に続く原発事故で故郷を離れざるを得なかった方たちへ、心ない中傷や誹謗をするということの残酷さを思うと、本当に悲しい気持ちになります。被災者になるということは、日本に住んでいれば、明日は我が身です。だれでも被災者になるのです。好き好んで故郷を離れたわけではない、原発事故は福島の人たちが起こしたわけではありません。しかし、福島という地名に過剰に反応し、放射能汚染があると思っていまい、排除しようとする、そんな気持ちを持つ人がいることに日本人の心の貧しさを感じます。 また、原子力についても正しい知識を持たずに絶対的に拒否するか、安全だという公的機関の情報を鵜呑みにしてしまう、そんな日本人も多いのではないでしょうか。原発事故は科学の危うさを浮き彫りにしました。私たちは自分たちで制御できないものを作りだし、その有益性を享受していたわけですが、それは巨大な危険の上に成り立っていたもので、その危険をコントロールできていると勘違いしていたのです。いや、危険性を懸念しながらも、そんなことは起こらないだろうと思い込んでいたのです。震災直後によく聞いた言葉「想定外」、大きな自然災害の後に言われますが、本当に想定外だったのでしょうか。想定外にして、対策していなかったのではないでしょうか。 東日本大震災から6年経った今、子供たちに科学を教えていく中でこれからも大事にしたいと思うことは、なぜかと自ら考える習慣を養うことです。自然災害を想定外だったと片付けるのではなく、何か出来なかったのかなと考えて欲しいのです。情報を鵜呑みにせず、本当かなと考えて欲しいのです。そんな習慣を養うことが、子供たちの未来に安全をもたらしてくれると信じたいです。 |
来月のプログラムについて
4月のテーマは「植物の色、食品の色」です。